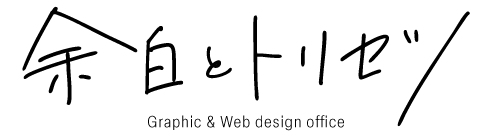“整える”とは、足りない自分を埋めることでも、完璧を目指すことでもありません。
いまある自分をやさしく見つめ、もう一度、心の奥にあるリズムを聴き直すこと。
「余白を整えるトリセツ」が生まれた背景と、そこに込めた想いを綴ります。
きっかけは「頑張れない」から始まった
「もう少し頑張れば、きっと変わる」と思い続けていた頃、心も体も少しずつ動かなくなっていきました。
やる気が出ないのに、止まることが怖かった。
“何かを成し遂げること”だけが、自分の価値だと信じていたからです。
けれど、ある日ふと気づきました。
どんなに外側を整えても、内側の声を置き去りにしたままでは、どこかがずっとチグハグなままだということに。
そのとき初めて、“整える”という言葉の意味を、自分のために使ってみようと思いました。
それは「頑張れない自分を責めない」という、小さな勇気の始まりでもありました。
「整える」は、自分を責めない選択
多くの人が「整える」という言葉に、“片づける”“減らす”“変える”というイメージを持っています。
けれど、本当の“整える”は、何かを減らすことではなく、自分の中の大切な順番を思い出すことなのだと思います。
あれもこれも手放せないときは、どれもきっと大切だった。
だからこそ、一度立ち止まって、静かに見直す時間が必要になります。
「どれを優先したら、私は心地よくいられるだろう?」
そう問いかけることで、自分への信頼が少しずつ戻ってくる。
整えることは、完璧に揃えることではなく、“いまの自分をそのまま受け入れる”という、
やさしい選択の積み重ねなのかもしれません。
外側ではなく、内側を見直すデザイン
私はデザイナーとして、ずっと「外を整えるだけでは、世界は本当の意味で整わない」と感じてきました。
根っこにある想いはいつも同じ——内側が整っていなければ、どんなデザインもハリボテに見えてしまうということ。
それでも、クライアントに理解してもらうために、言葉や形を何度も工夫し、試行錯誤を重ねてきました。
けれど次第に、思い描く本質を形にできないもどかしさが、心の奥に静かに積もっていったのです。
だからこそ、“デザイン”という言葉の意味を、もう一度見直してみたくなりました。
デザインとは、飾ることではなく、内側にある意図や想いを、形にして伝えること。
つまり、外側を整えることよりも先に、自分の中のリズムや価値観を調律することが大切だと。
“余白を整える”という考え方は、そんな気づきから生まれました。
それは、モノでも時間でもなく、心の中の空間を整えるという発想。
静けさや間をつくることで、ようやく“本当の自分”が顔を出すのです。
トリセツづくりは、“立ち返る場所”をつくること
「余白を整えるトリセツ」は、働き方や生き方を変えるためのマニュアルではありません。
それは、自分が迷ったときに立ち返るための地図のようなもの。
どんなに前向きに進んでいても、心がふっと迷う瞬間は誰にでもあります。
そんなとき、過去の自分が書いた言葉や、心の整理の記録に触れると、
“ああ、私はこう在りたかったんだ”と優しく思い出せる。
その“立ち返る場所”を持っているだけで、人は不思議と軽くなれます。
トリセツをつくることは、未来の自分へ「大丈夫だよ」と手紙を送るような行為。
整えるとは、決して止まることではなく、“もう一度、はじめられる準備”をすることなんです。
終わりに──「整える」は、未来へのやさしい準備
“整える”とは、自分を変えるための努力ではなく、
これから先の時間を心地よく生きるための、やさしい準備。
誰かの期待でも、効率でもなく、
自分の内側の声に合わせて生きることが、
「余白を整えるトリセツ」の本当の目的です。